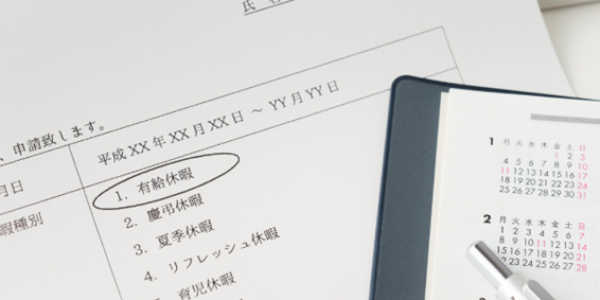従業員満足度の中でも「福利厚生の満足度」は、従業員の働く意欲や働きやすさに関わるため、会社にとって重要な指標の1つです。
本記事では、福利厚生の満足度が重要な理由、従業員満足度が高くなる福利厚生はどのようなものかについて紹介します。
1.福利厚生についての従業員満足度は働きやすさを表す
福利厚生についての従業員満足度が高い会社ほど、従業員が働きやすい会社の可能性があります。福利厚生には、働き方に関する制度や労働時間に関する制度など働きやすさに関わる内容が含まれるからです。
実際に、福利厚生に関する調査では、健康づくりの支援や余暇活動の支援などの福利厚生を実施していない会社に比べて、実施している会社の方が、「働きやすい」または「どちらかといえば働きやすい」と答える社員が多いことがわかっています。
参照:「働きやすい・働きがいのある 職場づくりに関する調査 報告書」(PDF)| 厚生労働省
働きやすさが高い会社は、従業員の仕事に対する意欲も高く、会社への定着率も高い傾向があるため、従業員満足度を測る指標の1つである福利厚生は、会社が行うべき重要な取組の1つと言えます。
そもそも従業員満足度とは?
従業員満足度(Employee Satisfaction;ES)とは、「働きがい」や「働きやすさ」、「職場環境」など、会社が用意する制度や人間関係について、社員側からの満足度を表す評価指標のことです。
「労働人口の減少」や「働く人々にニーズの多様化」などの社会情勢から、企業の雇用管理において従業員満足度を重視する企業が増えています。
福利厚生は、従業員満足度の中で職場環境に関する指標の1つで、社員の働きやすさやワークライフバランスに関わる評価項目に当ります。
2.従業員満足度が高くなる福利厚生制度や施策
令和2年度版厚生労働白書から、従業員満足度が高くなる福利厚生制度を3つ解説します。
- 健康管理を補助する制度
- 休暇に関する制度
- 働き方の多様化に対応する制度
健康管理を補助する制度
健康管理の促進や補助に関する福利厚生は、従業員からのニーズが高いため満足度が高くなる制度の1つです。
実際に、福利厚生に関して行われた調査では、必要と感じる福利厚生の中で「人間ドックの受診補助」と答えた人の割合が最も高かったことからも、健康管理に関するニーズの高さが推察できます。
また、従業員の健康管理を補助する福利厚生には、次のようなものがあります。
- 法定外の健康診断など、保健・医療面の補助
- メンタルヘルス相談など心の健康に関する支援
- フィットネスクラブの利用補助
参照:「働きやすい・働きがいのある 職場づくりに関する調査 報告書」(PDF) | 厚生労働省
例えば、参照先によると、上記3点の福利厚生を用意している会社は、用意していない会社と比べて働きやすいと感じる社員が多いことがわかっています。
なお、健康に関する福利厚生については次の記事で詳細に解説しています。
福利厚生で健康支援が重要視される理由や制度と施策例を解説
休暇に関する制度
法定外休暇に関する福利厚生は、ワークライフバランスを重視する社員からのニーズが高く、満足度が高くなる制度であるといえます。
休暇に関する福利厚生は、法律で決められた「法定休暇」と会社が独自で用意する「法定外休暇」があります。
法定外休暇に関する福利厚生の一例として、次のような制度があります。
- 病気休暇制度(有給休暇以外)
- 慶弔休暇制度
- 有給休暇の日数の上乗せ
- リフレッシュ特別休暇制度
特に、慶弔休暇制度は、多くの企業で用意されている福利厚生であるため、用意されていない場合、従業員の満足度低下につながる可能性があります。
なお、休暇制度に関する福利厚生については次のコンテンツで詳細に解説しています。
福利厚生の休暇とは?種類から週休3日制まで基礎知識を解説
働き方の多様化に対応する制度
様々な背景を持つ従業員が働く会社では、働き方の多様化に対応する制度や施策も、従業員満足度を高める福利厚生です。
また、多様な働き方を認める福利厚生を用意している会社は、育児や介護などを抱えた従業員でも仕事量を調整して働けるため、会社への定着も期待できます。
働き方の多様化に対応する福利厚生としては、勤務時間や働く場所に関する制度があります。
- リモートワーク制度
- 時短勤務や時差出勤の拡充
- 定時退社を推進する制度(ノー残業デー)
例えば、勤務時間を短くする「時短勤務」や、出勤時間を混雑のピークからずらす「時差出勤」など、幅広いワークスタイルを用意することで、様々なライフスタイルの従業員の満足度向上が期待できます。
また、業務内容によっては、リモートワーク制度を導入することで、通勤や営業先への移動時間を削減し、労働生産性の向上につながる可能性があります。
なお、リモートワークに関する福利厚生については次のコンテンツで詳しく解説しています。
リモートワークを福利厚生に導入する方法と在宅勤務支援策を解説
3.導入例が多い福利厚生制度や施策のトレンドも把握する
導入例の多い福利厚生を把握しておくことは従業員の満足度を維持する上で重要です。
導入例の多い福利厚生が自社にない場合、競合他社と比較した際の従業員満足度を下げてしまう可能性があるためです。
次の表は、中小企業が導入している福利厚生の種類を調査したものです。特に導入率が高い福利厚生は「慶弔休暇(87.7%)」「慶弔見舞金(86.0%)」「育児休業(72.4%)」です。
福利厚生 |
導入率 |
住宅手当 |
46.0% |
食堂・昼食補助 |
23.5% |
育児休業 |
72.4% |
介護休業 |
50.2% |
慶弔休暇 |
87.7% |
慶弔見舞金 |
86.0% |
永年勤続表彰 |
47.6% |
社員旅行 |
43.2% |
財形貯蓄 |
32.5% |
その他 |
7.9% |
特にない |
1.6% |
引用:令和3年度中小企業実態調査委託費 中小企業の経営力及び組織に関する調査研究 報告書(PDF) 「5.人事評価制度、給与体系、福利厚生施策」③福利厚生施策(1)実施している福利厚生施策 p.61|中小企業庁
なお、福利厚生は、働きやすさや人材定着のほかにも雇用面に影響を与える可能性があります。
そのため、求職者が比較検討する競合他社の福利厚生と差が生まれないよう、導入例の多い福利厚生を把握して必要に応じて導入検討する必要があります。
その際、導入例だけではなく、社会情勢にあった福利厚生のトレンドも把握しておきましょう。福利厚生のトレンドについては次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生のトレンドは従業員個人の利益から企業を成長させる力へ
(執筆 株式会社SoLabo)
生22-6463,法人開拓戦略室